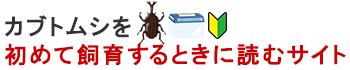PR
知らなくてもカブトムシを飼うには支障ない。でも、子供の質問に答えられないと、なんかモヤモヤする。親として、少し残念な気分になる…。
子供とカブトムシを飼っていると、そんな経験をすること、ありますよね^^;
親ならば、子供の質問にはズバッと答えたいもの。僕は、小学6年生の息子と2年生の娘の父親です。
このページでは、子供に質問されても戸惑わないため、カブトムシに関する豆知識をQ&A形式でまとめて紹介します。
目次
- 1 カブトムシに別の名前ってあるの?
- 2 カブトムシは何の仲間?
- 3 カブトムシは何種類いるの?
- 4 カブトムシのギネス記録は?
- 5 カブトムシのホワイトアイ、レッドアイって?
- 6 カブトムシの持ち方を知りたい
- 7 カブトムシの色は、なんで黒いの?
- 8 カブトムシのオスの角は、なんで急に生えてくるの?
- 9 カブトムシの裏側に毛が生えているのは、なぜ?
- 10 カブトムシは、どれくらいの力があるの?
- 11 カブトムシは、どうやって飛ぶの?
- 12 カブトムシは鳴くの? どんな鳴き声をしているの?
- 13 カブトムシも寝るの?
- 14 カブトムシは、人間になつく?
- 15 カブトムシとクワガタの成虫は、一緒のケースで飼っちゃダメ?
- 16 カブトムシに天敵はいる?
- 17 カブトムシの幼虫は共食いをする?
- 18 カブトムシの幼虫の性別は、どうやって見分けるの?
- 19 カブトムシは冬眠する?
- 20 プランターに幼虫がいたけど、カブトムシ?
- 21 カブトムシは、絶滅危惧種って本当?
- 22 まとめ
カブトムシに別の名前ってあるの?
「カブトムシ」は、日本での名前。
カブトムシの世界共通の名前は、「Trypoxylus dichotomus」といいます。
「トリュポクシュルス ディコトムス」と発音するのだとか^^; なにかの呪文みたいですね。
スウェーデンの生物学者であるカール・フォン・リンネが名づけ親です。
カブトムシは何の仲間?
カブトムシは、コガネムシの仲間です。
コガネムシの分類の中の「カブトムシ亜科」に属します。
カブトムシは何種類いるの?
カブトムシは世界で約1,600種類、日本には5種がいるとの報告があります。
このほか、日本で1匹だけ取れた記録がある激レアなカブトムシが1種類いるそうです。
世界で一番重いカブトムシは、ゾウカブトムシ。その名のとおり、ゾウみたいにどっしりとした体格をしています。

一番大きいカブトムシは、ヘラクレスオオカブトです。夏の時期、カブトムシ売り場で見かけることがありますね。
角が大きく発達しているのが特徴です。
ヘラクレスオオカブトの全長は、45~180mm。日本のカブトムシの2倍以上の大きさがあります。

ただ、僕が一番カッコイイと思うのは、やっぱり日本のカブトムシ。黒いツヤのあるボディがたまりません^^

カブトムシのギネス記録は?
カブトムシの長寿に関するギネス記録は、今のところありません。通常でいうと、カブトムシの成虫の寿命は約2か月です。
大きさに関するギネス記録は、俳優の哀川翔さんが育てた88.0mmのカブトムシです。
僕が今までに育てたカブトムシは、最大で85.0mm。哀川さんにはわずかに及びませんでした^^;

一般的な国産のカブトムシのサイズは、オスの場合は27~75mm、メスの場合は33~53mmくらいです。
僕は出会ったことがないですが、27mmのオスって…かなり小さい! きっとかなり可愛らしいでしょうね^^
カブトムシのホワイトアイ、レッドアイって?
ホワイトアイ、レッドアイは、突然変異のカブトムシです。その名のとおり、白または赤い目をしています。

(出典:オオクワ京都昆虫館)
僕が住んでいる石川県にある「ふれあい昆虫館」によると、ホワイトアイが生まれる確率は約2万分の1だそうです。
レアなカブトムシなだけあって、オークションでは1匹1,000円以上の高値が付くことが多いですよ。
ちなみに、僕は、ホワイトアイ、レッドアイは、さほど欲しいとは思いません。
目が死んでいるみたいで、好きではないです…(好きな方、すみません。汗)
カブトムシの持ち方を知りたい
カブトムシのオスは、胸角(きょうかく)という小さい角をつまんで持ちます。簡単ですね。

ただ、木などにつかまって離してくれないときは、かなり厄介。
そんなときは、次の方法を試しましょう。
1つめの方法では、カブトムシが自分からパッと脚を開いてくれることが多いです。
2つめの方法では、カブトムシに空中散歩をさせる要領で木から引きはがします。
いずれの方法にしても、強引にするのは止めましょう。脚が取れてしまう惨事にもなりかねません(汗)
なお、カブトムシの別の持ち方として、体の横を持つ方法もあります。
ただ、これでは落としてしまう可能性が高いです。カブトムシは、脚をバタつかせて必死で抵抗します。

オスは、やはり胸角を持つのが安全です。
メスの場合は、脚の爪で引っ搔かれないように軍手をして、両手で体を包み込むようにして捕まえるのがおすすめです。
隙間からメスが逃げないよう、指はガッチリ閉じておいて下さい。
カブトムシの色は、なんで黒いの?
カブトムシが黒いのは、敵から見つかりにくい色だからです。
カブトムシは夜行性。闇に紛れる黒なら、敵に見つかりにくいですよね。

昼間、木の根元や幹にいても、黒なら目立ちません。

ただ、黒い分、直射日光は苦手。太陽光を集めやすいです。
直射日光が当たる環境では、カブトムシは10~20分で死んでしまいます。
なお、カブトムシの色には若干の個体差があります。真っ黒のもの、茶色っぽいもの、赤みを帯びたものがいます。
カブトムシのオスの角は、なんで急に生えてくるの?
幼虫の頃は角なしのカブトムシ。蛹になったとき、急に生えてきます。
ただ、名古屋大学大学院生命農学研究科の後藤寛貴博士を中心とした研究結果によると、カブトムシのオスの角は、実は、幼虫の頃から存在しているそうです。
小難しい話なので、ザックリと説明しますね。
幼虫の時期、カブトムシの角は、幼虫の頭の中に折りたたんだ状態で収納されています。
そして、蛹になるときに体液が送り込まれることで、角が急にニョキッと生えてきたように見えます。

たしかに、幼虫の時期から角が生えていると土の中に潜りにくいですよね。土から受ける抵抗がハンパなさそう^^;
幼虫の頃に角なしなのは、理に適っています。
カブトムシの裏側に毛が生えているのは、なぜ?
カブトムシの裏側に毛が生えている理由は、ハッキリしていません。
カブトムシの生態から考えると、お腹の毛には「木に止まっているときに滑り止めになる」「土に潜るときに、体が直接汚れるのを防ぐ」くらいの役割があると想像できます。
でも、正確なことはわかっていません。

カブトムシは、どれくらいの力があるの?
カブトムシは、自分の体重の20倍ほどの重さを引っ張ることができるそうです。
飼育ケースの蓋がしっかり閉まっていないと、難なくこじ開けて脱走できるのも納得ですね^^;
カブトムシを飼うときは、脱走されないよう、くれぐれも気をつけましょう。

カブトムシは、どうやって飛ぶの?
カブトムシは、体の中にしまってある後ろばねを広げ、上下に素早く動かして飛びます。
体の外側から見える前ばねは、背中や後ろばねが傷つくのを防ぐためのもの。飛行には使いません。
後ろばねは、普段、2つ折りにして、前ばねの中に大切にしまってあります。

一説によれば、カブトムシが飛行できる距離は、1kmにも及ぶそうですよ。
カブトムシは鳴くの? どんな鳴き声をしているの?
カブトムシは、「シューシュー」「ギュウギュウ」「ギュウィン・ギュウィン」と鳴くことがあります。
これは、カブトムシが敵を威嚇したり、求愛行動をとったりするときに、腹部と前ばねを擦って出す音。
前ばねは、カブトムシの体の外側にある固い羽のことです。
このほか、僕の経験上、メスが産卵のために土に潜っているときには、ケースから頻繁に「ギー、ギー」といった音がします。
これは、脚の爪でケースの底を引っ掻いているときに出る音です。
また、幼虫を飼育しているときには、「カツカツカツカツ…」「パキッ」といった音がよく聞こえます。
これは、幼虫たちが腐葉土を食べているときの音です。
幼虫たちは、音を出すことによって、お互いに近づき過ぎないようにしています。
カブトムシも寝るの?
カブトムシは夜行性の虫。
日中は、落ち葉の下や土の中で寝ています。カブトムシにはまぶたがなく、目は常に開きっぱなしの状態です。

逆に、夜はカブトムシの活動時間。
僕が飼っているカブトムシたちは、深夜1~5時頃が特に活発です。
「ブーン、バタバタバタバタ」と、ケースからカブトムシが飛ぶ音がして、うるさいくらいです^^;
カブトムシは、人間になつく?
正直、なんともいえません。
ただ、カブトムシをはじめとする昆虫の行動は、本能によるものが多いです。
昆虫には、脳はあるものの、ごく小さいです。思考に欠かせない「大脳」はありません。
とはいえ、本当のところは、カブトムシに聞いてみないとわからないですよね。
僕としては、用意してあげた昆虫ゼリーをカブトムシがガツガツ食べてくれるのを見るだけで、十分です^^
「買ってあげた甲斐があったな…」と、勝手に満足しています。

カブトムシとクワガタの成虫は、一緒のケースで飼っちゃダメ?
カブトムシとクワガタの成虫は、別々のケースで飼育することをおすすめします。
オス同士は、特に喧嘩をしやすいです。

やむを得ず一緒に飼う場合でも、幅30cmのケースに対して飼育する数は2~3匹に留めて下さい。
まとめて飼育するほど、喧嘩が起りやすいです。
そして、できれば早々に新しいケースを用意して、分けて飼育するようにしましょう。
カブトムシに天敵はいる?
昆虫界の中で最強といえるカブトムシにも、天敵はいます。
カラスやイノシシ、タヌキが、その一例です。カブトムシの幼虫にとっては、モグラが天敵です。

また、カブトムシを採集する人間も、厄介な天敵といえるかもしれません^^;
カブトムシの幼虫は共食いをする?
カブトムシの幼虫が共食いをすることは、基本的にはありません。
幼虫が食べるのは、広葉樹の腐葉土です。
上述のとおり、カブトムシの幼虫は、互いに音を出すことで近づきすぎないようにしています。
カブトムシの幼虫が共食いするなら、土を交換するときに、残骸を発見することがあっても良いはずですよね。
少なくとも、僕は、そのような幼虫を発見した経験は一回もありません^^;
カブトムシの幼虫の性別は、どうやって見分けるの?
カブトムシの成虫の場合、性別は一目瞭然ですよね。角があればオス、なければメスです。
カブトムシの幼虫の場合は、お腹の「Vの字」で判断します。
お腹に「Vの字」があればオス、なければメスです。

ただ、幼虫は、なかなかお腹を見せてくれません。性別を見分けるのは、正直、難しいです^^;
カブトムシは冬眠する?
カブトムシは、11~12月頃に幼虫の姿で冬眠に入ります。そして、3月中旬以降、気温が高くなるにつれて冬眠から目覚めます。
ただ、これは、野生のカブトムシや屋外で飼育した場合の話です。
室内で飼っているカブトムシの幼虫は、ほとんど冬眠しません。気温が保たれているからです。
たしかに、12~1月頃は活動が鈍くなり、土があまり減らなくなります。
ただ、全く動かなくなることはありません。
2月頃になれば、土を食べる量が少しずつ増えていきます。3月中旬以降には、また土をガッツリ食べるようになりますよ。
年中エアコンが効いた部屋で育てた場合、羽化するタイミングも早め。梅雨~初夏にかけて、成虫の姿で土から出てくる子が多いです。
プランターに幼虫がいたけど、カブトムシ?
プランターにいる幼虫のほとんどは、コガネムシです。
コガネムシは、別名で「ネキリムシ」ともいいます。草木の根っこを食べて枯らしてしまう害虫です。

カブトムシとコガネムシの幼虫を見分けるには、歩き方で判断するのが一番。
コガネムシの幼虫は、スタスタと器用に地面を歩けます。
一方、カブトムシの幼虫は、地面を歩くのが苦手。体をくねらせるだけで、前に進むことはできません。
地面を歩かせてみれば、一目瞭然で区別できますよ^^
カブトムシは、絶滅危惧種って本当?
日本にいるカブトムシのうち、コカブトムシは「準絶滅危惧種」です。
ただ、世界中の昆虫が急激に減少しているのはたしか。
BBCニュースによれば、「世界中の昆虫の40%が『劇的な減少率』で個体数を減らしている」そうです。
さらに「カブトムシなどは、ほ乳類や鳥類、は虫類と比べて8倍の速さで減少している」とのこと。
カブトムシをはじめとする昆虫たちが僕たちの前から姿を消す日が来ないよう、一人ひとりができる努力をしていきたいですね。

まとめ
このページでは、知らなくてもカブトムシを飼えるけれど、知っていると鼻が高い豆知識をまとめて紹介しました。
カブトムシを飼っていると、子供は、親である僕たちが思いもよらないような質問をしてくることがあります。
そんなとき、このページをこっそりみて、お子さんにズバッと答えてあげて下さいね^^