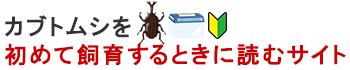PR
小学生の子供が夏休みの自由研究のテーマに選ぶことが多い「カブトムシ」。
僕の息子も、もれなくその一人でした(笑)
僕は、小学6年生の男の子の父親です。子供が小学1年生の頃からカブトムシを飼っています。
息子の自由研究を手伝う中でも、僕が一番感心したのが「カブトムシの体のつくり」でした。
カブトムシの体は、自然界で生き抜くのに実に合理的なつくりになっています。
そこで、このページでは、僕たち親子が調べたカブトムシの生態と体のつくりに関する情報を掲載します。
ぜひ、自由研究の参考にして下さいね^^
目次
カブトムシの成虫の生態と体のつくり
まず、カブトムシの成虫の生態と体のつくりからみていきましょう。
カブトムシの成虫の体は、木の上または土の中で過ごすのに適したつくりになっています。
カブトムシの成虫の生態は、次のとおりです。
カブトムシの成虫の体は、次の3つのパーツに分かれています。

カブトムシは、他の昆虫と同じく、胸から6本の足が生えています。
体の各部分の名称は、次のとおりです。

ここで、各部位の特徴をまとめてみました。
| 部位 | 特徴 |
|---|---|
| 目 | 明るさを感じ取るのに優れた複眼。小さな目が約2万個集まってできている。明るさの変化から敵やメスの動きを瞬時に察知する |
| 触覚 | 空気の流れや臭いを感じ取る。周りの環境や樹液の位置を感知するセンサーのような役割を果たす |
| 口 | オレンジ色のブラシ状の口。樹液を効率よく舐めとって食べる |
| 足 | 足は全部で6本。胸から放射線状に生えている。足先には鋭い爪があり、木にガッチリ掴まることができる |
| 気門 | 気門とは、空気が出入りする穴。胸と腹の側面に左右9個ずつある。口の周辺に気門がないことで、樹液で塞がって窒息死する心配がない |
このほか、カブトムシの体で特徴的なのが羽です。
カブトムシの羽は、前ばねと後ろばねの2種類。
前ばねは外殻と同じように固く、飛行に使う後ろばねを守ります。
後ろばねは、普段は、前ばねの下に2つに折りたたむようにして収納してあります。

カブトムシは、前ばねを左右に大きく開き、後ろばねを広げてすばやく上下させることによって飛びます。
カブトムシが飛んでいると「ブーン」と大きめの音がするので、すぐにわかりますよ^^
このように、成虫の体は、カブトムシが自然界で生きるのに都合の良いつくりになっています。
また、カブトムシの成虫は、オスとメスで体のつくりが大きく異なります。
| カブトムシの成虫(オス) | カブトムシの成虫(メス) |
|---|---|
 |  |
| ・木の幹に馴染みやすい赤茶色の体 ・大小2本の角がある。樹液やメスを奪い合うときに使う。 | ・土や枯れ葉に馴染みやすい黒褐色の体 ・土に潜りやすいよう、角がなく、頭が小さい ・土に潜っても汚れないよう、体全体にうっすら毛が生えている |
カブトムシのオスは、頭に角が生えているのが大きな特徴です。
カブトムシのオスにとって、角は喧嘩に欠かせない武器です。
オスは、一匹でも多くの子孫を残すため、樹液とメスの争奪戦に明け暮れて過ごします。
カブトムシのメスは、頭が小さく、オスに比べて体が毛深いのが特徴です。
メスの体は土に潜りやすく、汚れにくいつくりになっています。
メスは、産卵のため、一日の大半を土の中で過ごします。
カブトムシの成虫の断面図をみてみよう
では、カブトムシの成虫の断面図をみてみましょう。
下の図は、僕がザックリと描いたものです。
正確な位置・形を知りたい人は、専門書を見てくださいね(苦笑)
カブトムシの成虫の断面図

カブトムシの体の断面図をみてみると、人間と同じような臓器が入っているのに気づきます。
呼吸器・消化器・生殖器・血管系のほか、体を動かすための筋肉も発達しています。
人間との大きな違いは、カブトムシの体には骨がないことです。カブトムシの体は、丈夫な殻で覆われています。
また、カブトムシの血管は、細長い管である心臓1本のみ。
心臓から血液が染みだし、体全体に行き渡る仕組みになっています。カブトムシの血の色は透明です。
カブトムシの体は人間と多少の違いはあるとはいえ、その小さな体に生きていくために必要な臓器をぎゅっと詰め込んでいることがわかります。
カブトムシの幼虫の生態と体のつくり
次に、カブトムシの幼虫の生態と体のつくりをみていきましょう。
カブトムシの幼虫は、もっぱら土の中で過ごします。餌となる腐葉土を食べて、自らの体を大きく育てます。
カブトムシの幼虫の生態は、次のとおりです。
カブトムシの幼虫の体は、次のようになっています。

カブトムシの幼虫は、柔らかい体をしているのが特徴です。
柔らかい体は土に馴染みやすく、わずか数秒で土の中に潜れます。
また、カブトムシの幼虫は、大きく発達した顎が目立ちます。
丈夫な大あごは、土をガツガツ食べるのにとても便利です。
顎とは反対に発達が著しく乏しいのは、目です。
カブトムシの幼虫は、基本的に土の中で過ごすことから、はっきりとした目がありません。
幼虫同士は、近づきすぎないように土の中で音を出し合い、互いの位置を確認し合って生活しています。
カブトムシの幼虫は、腐葉土をたくさん食べて大きく育つことに特化した体になっています。
カブトムシに幼虫の断面図をみてみよう
続いて、カブトムシの幼虫の体の断面図もみてみましょう。
カブトムシの幼虫の断面図

断面図から、カブトムシの幼虫は消化器が太く発達しているのがわかります。
自らの体を大きく育てるのが、幼虫の時期の務め。
幼虫の体は、腐葉土をたくさん食べて消化できる仕組みになっています。
幼虫のオス・メスの見分け方
ここで、カブトムシの幼虫の性別を見分ける方法についても紹介しておきます。
飼っている幼虫がオス・メスのどちらなのかは、気になるところですよね。
カブトムシの幼虫の性別を見分けるには、幼虫のお腹の内側を見ます。
内側に黒っぽい「Vの字」が薄っすらあればオス、なければメスです。

ただ、性別の確認のため、幼虫のお腹を見ようとしても、難しい場合が多いです。
土から出すと、幼虫はすぐに体をねじったり、丸めたりしてしまいます。

無理にお腹を見ようとして幼虫を弱らせることがあっては、本末転倒です(汗)
飼っているカブトムシの性別は、成虫になって土から出てくるまで楽しみに待つ方が現実的かもしれません^^;
カブトムシの蛹の生態と体のつくり
最後に、カブトムシの蛹の生態と体のつくりをみていきましょう。
カブトムシの蛹は、蛹室の中で羽化する日までじっとして過ごします。
蛹室とは、カブトムシの幼虫が土の中に作った縦長の空洞のことです。

羽化とは、カブトムシが蛹から成虫になることをいいます。
カブトムシの蛹の生態は、次のとおりです。
カブトムシの蛹の体のつくりは、次のとおりです。

蛹になると、成虫の体にかなり近づきますね^^
カブトムシの蛹が成虫と大きく違うのは、背中部分に敵から身を守るための仕組みがあることです。
カブトムシの蛹の体は、背中のシワの部分が鋭い刃のようになっていて、近づいてきた敵を挟み切れるようになっています。

蛹はお腹の部分をくねらせることで、体を多少動かすことができます。
カブトムシの蛹の体は、外殻の内側では成虫になるための大きな変化を迎えつつも、外敵から自分の身をしっかり守れるつくりになっています。
まとめ
このページでは、カブトムシの生態と体のつくりについてお話ししました。
カブトムシは、成虫のときは木の上か土の中、幼虫・蛹のときは土の中で過ごします。
カブトムシは、自然界で生き抜くため、時期ごとに最も適切な姿に体を変えて生活しています。
特に幼虫から蛹・成虫への体の変化は大きく、同じ昆虫とは思えないほどですよね。
あなたのお子さんが自由研究をまとめるとき、このページの内容が役立てば、うれしいです^^
なお、カブトムシの断面図について「子供のために良い本を探しているのに見つからない!」とのお問い合わせをよくいただきます。
おすすめの本を載せておきますので、お困りの方は、ぜひチェックしてみて下さい。